理事長ごあいさつ
私立学校は、それぞれの建学の精神を持ち、その具現化を行うことにより、公立学校とは異なる教育機関としての存在価値があります。
本学園創立者である大多和音吉(1887~1957)は、若き時代に一介の海軍兵としてアメリカに遠洋航海し、日本でも洋装の時代が来ると予感しました。明治時代末期のことです。苦労して育ててくれた母への思いから、音吉は女性が自立できる社会の到来に貢献したいと思っていました。海軍を退役し、ミシン会社に就職し、ミシンについて学びました。音吉の妻、タカ(1893~1989)はミシン技術の指導を行い、夫婦二人三脚で営業に尽力しました。しかし、まだ洋装が普及していない大正時代に、しかも地方においてのミシン販売は大きな困難がありました。会社での活動に限界を感じ、退社し、夫妻で学校を開校します。それが本学園前身「松江ミシン裁縫女学院」で、大正13(1924)年のことです。
開校したものの、ミシンや洋裁の需要は増えません。ただし、女子教育の需要は、少しずつ増えてきました。人間教育に価値を見出した音吉は、その根幹を探しました。宗教や哲学に触れ、たどり着いたのが「モラロジー」です。「モラロジー(道徳科学)」とは、法学博士・廣池千九郎(1866~1938)が創建した総合人間学です。音吉は、倫理道徳の研究を推進し、人間としてのよりよい生き方と住みよい社会の実現をめざし、明るい未来を拓こうとするモラロジーの目的に共感し、道徳教育の推進を考えました。
こうして本学園の二つの教育の柱が確立しました。一本は、次の時代を見据え、先んじて行う「先見・先行教育」です。もう一本が、人間としてよりよい生き方をめざすモラロジーによる道徳教育です。
大正、昭和、平成、令和と時代が移り変わる中で本学園の歴史は、時代の波に飲み込まれそうになったこともありました。そうした中で、不易(変えるべきでないもの)と流行(変えるべきもの)を見極めながら歩んで、今日に至っています。建学の精神こそが、本学園の教育内容を決定する価値基準だと考えています。
創立から100年を迎えようとしている今日、存在価値のある学校であり続けることは、容易なことではありませんが、建学の精神を基盤として公教育の一翼を担い、本学園の校名「開星」の由来である「社会の発展に役立つ有望な人材の育成」に向け、今後とも尽力してまいります。
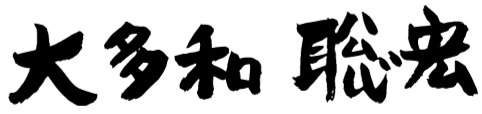
校長ごあいさつ
開星中学校・高等学校は、2024(令和6)年に創立100周年を迎えます。島根県松江に立地する本校の歩んできた道のりは、県内の他の学校には見られない独自性を有しておりますが、その底流にあったのは「品性の向上をはかる」「地域のための学校」という考えです。
本校は、島根県はもとより日本、世界に貢献できる教育機関となることを使命としております。地域とともに未来社会をデザインし、経営基盤を拡充することにより、島根と世界を繋ぐ津梁・架け橋となる有望な人材を育てることと併せて、研究開発の進展にも貢献して参ります。
本校は、未来を担う世代の希望の学び舎であります。未来の世代に何を残すべきか考え、「実が稔る種や苗木」を植え続けていくことが今という時を共有している私たちの責務です。人づくりは、地域発展の礎であります。
「強い者、賢い者が生き残るのではない。変化できる者が生き残るのだ。」とは、進化論で有名なダーウィンの言葉です。次の100年に向けて、本校も、これまで長きに渡って積み重ねてきた伝統を守りつつ、新しい時代に求められる教育を充実させ、より良い学校になることを目指して進化を続けていきます。生徒皆さん一人一人の個性を尊重し誰一人取り残すことのない学びの場を提供できるよう、私も誠心誠意努めて参ります。
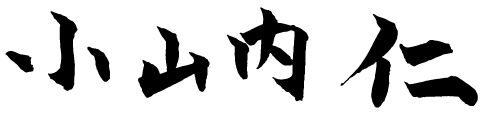
同窓会長ごあいさつ

野津 直嗣
同窓会長・松江市議会議員

私は開星高校卒業生の第1期生です。入学時には松江第一高校、卒業時には開星高校と校名が変更されました。 部活はサッカー部で、この時代には野球部、柔道部など多くの県内スポーツ大会で開星高校が活躍し始めた時代です。部活終わりに現在の校舎やグラウンドから見る松江の夜景が綺麗であったのを想い出します。私は決して勉強ができるタイプではなく、部活の時以外は居眠りする事も多く、よく先生に怒られていました。現在の教育環境と違い、先生も自由、生徒も自由、その代わり怒られる時は本気で怒られ、本気で言い返した日々が懐かしいです。卒業後はサッカーのコーチやバンド活動を中心にこの街で頑張りました。現在、市議会議員を4期務めさせて頂いていますが、その中で気づいた事があります。家政・第一・開星高校の卒業生の多くが好奇心と挑戦心を持って、松江市内や県内外の多くで活躍している姿に多く出会ってきた事実です。キャリア教育という言葉もない時代、まさしく学校や生徒、先生と生徒、生徒と生徒、人と人とが熱量のあるコミュニケーション拠点こそがまさしく学校にあった気がします。そして「学問」からは学べなかったであろう、人として大切な事を開星高校は教えてくれていたのではと思います。インターネットの普及、多様化・細分化する価値観、身体力の低下など教育の低下が著しいと言われています。母校・開星高校が多くの熱量を放ち続ける学校であるために同窓会一丸となって支えていきたいと思います。現在も母校で学ぶ子どもたちのため、また未来の母校で学ぶこどもたちの未来づくりのために多くの同窓生の皆様のご協力とご支援を何卒宜しくお願いします。